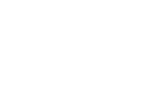特色ある教育活動
福井ブロック
未来を切り拓く生徒の育成をめざして(福井市:明倫中学校)

「自立した学び手として、他者や社会と自らの学びをつなぐ生徒の育成」をテーマに、公開授業研究会を行いました。青森県や大阪府からも参観者を迎えるなか、公開された授業は3年国語『故郷』、3年保健・体育『マット運動』、2年英語『Unit6 Research Your Topic』。木村優先生(福井大学大学院教授)にも御指導、ご講演をいただきました。どの授業でも生徒達は自分の考えを言葉で、文字で、身体表現で積極的に発信し、また、他の生徒の発信を受け止め、さらに自分の考えを深め発信していく姿が見られました。生徒からも「自分達で考えた課題を追究していくことが楽しい」「友達の意見を引き出すことが面白い」という振り返りが聞こえました。
ふるさと福井の良さを発見・発信しよう(福井市:光陽中学校)

総合的な学習の時間を中心に、ふるさと学習を行っています。
ふるさと福井の良さを発見・発信し、自分たちが今後の福井の発展のためにできることは何かを考えることで、これからの社会を主体的に生き抜く、たくましい人間の育成をめざします。
「地域に根ざした生徒会活動」(福井市:明道中学校)

福井市明道中学校の生徒会活動の一環として、7月に「福井城址お堀の灯り」の式典に参加しています。今年で15回目(2024年)を迎えるこのイベントは、福井空襲や福井震災で亡くなった人々を鎮魂する行事であります。
生徒たちは亡くなった方に鎮魂の意を捧げるための『鎮魂の灯り』と、将来の希望を願うための『希望の灯り』の2種類の灯籠を作成し福井城の広場に置きました。地域の人たちと一緒に当時のことについて詳しく学ぶ良い機会となりました。
明道中学校の生徒会は、ほかにも学校の前を流れる底喰川の清掃を、地域の人や高校生と協力して美化活動に取り組んでいます。
【SHIN化プロジェクト】(福井市:進明中学校)

○生徒が主役の三者懇談会
3年生保護者懇談会(7月)は、生徒が保護者と担任に向けて、「自分の学び」を発表する場
○先輩が後輩へ自分の学びをつなぐ
2年生が1年生へ「自分の学びの成果報告」「成長の分析」を発表する場
1年生が2年生へ「質疑応答」「自分の学びへの活かし方」を発表する場
地域の宝(生徒)によるボランティア活動(福井市:成和中学校)

校区の公民館で行われる行事に、吹奏楽部や茶華道部、その他有志がボランティアとして運営に参加しています。また、まちづくり協議会の「地域・未来への意見交換会」において、中学生として「地域の将来像」や「中学生の果たす役割」などについて意見交換を行っています。
これからも、地域を愛する生徒を育てると同時に、地域から愛される生徒を育てていきます。
「My Learning」(福井市:安居中学校)

・教科学習や総合、特別活動等で「何を学んだか」「自分はどう変わったか」といったことを、
異学年小グループやポスターセッションで発表・交流します。
・地域の方や保護者にも参加を呼びかけ、皆で学びを実感する機会となっています。
生徒同士が語り合う「語らい会」(福井市:大安寺中学校)

総合的な学習の時間で行っている探究活動の成果や生徒会が設定したテーマについて、異学年の生徒が混在するグループで話し合う「語らい会」を定期的に行っています。
「語らい会」では、互いの学びや考えをじっくりと語り合う「対話」を通じて、多様なものの見方や考え方を共有し、新たな気づきを得ることを目指しています。
各クラスターの団結旗を掲げて(福井市:至民中学校)

平成20年(2008)の移転開校以来、3つの学び(異学年クラスター、教科センター方式、地域連携)を大切にしてきました。
学校祭の活動の中で制作された各クラスターの団結旗は、生徒たちが毎日必ず通る葉っぱのひろばに1年間展示されます。また、卒業3年後の生徒たちが18歳の年に、公民館にもう一度掲げられています。
学校教育目標「未来につながる学力の育成」を目指し、研究主題を「学びのストーリーをデザインする」と設定しています。各教科・領域で、5つの至民型キー・コンピテンシーの育成を図っています。
3年生伝統の「灯中ソーラン」(福井市:灯明寺中学校)

毎年、学校祭で踊る3年生の「灯中ソーラン」。
クラスで振り付けを工夫し、気迫と一体感が感じられる3年生のソーランを見て、
1・2年生は伝統を受け継ぎます。
社会貢献活動(福井市:藤島中学校)

本校では公民館や自治会と協力しながら社会貢献活動を行っています。25年以上続いている活動です。本校はクラウド班といわれる学年を解いた縦割り班での活動を年間を通して行っており、ここ数年は社会貢献活動をこのクラウド班で行っています。地域神社の境内の清掃や河川の草刈り、道路脇の花壇の整備など地域に根ざした学びの創造を目的に取り組んでいます。
「遠泳大会・和楽器演奏会・岩のり採り」(福井市:国見中学校)

地域の方々に船を出していただいて開催する「遠泳大会」(地域の方と海岸清掃後に実施)や、地域人材を活用した「和楽器演奏会」(1年箏、2年檜三味線、3年和太鼓 福井駅前で演奏披露とふるさと国見のPRを実施)、採取から加工まで行う「岩のり採り」など、国見独自の教育活動を通して、地域貢献意識や、ふるさとを愛し誇りに思う心を育てている。
未来へつなぐ『大東愛プロジェクト』(福井市:大東中学校)

「行きも帰りもワクワクする楽しい学校にしたい」という願いのもとに立ち上がった『大東愛プロジェクト』。学年を超えた話し合いや生徒会活動などを通して、自分はもちろん、仲間、学校、家族、地域を愛し、誇りに思い、全校で愛情にあふれた幸せな学校をめざしています。
現在、総合的な学習の時間には、『地域の宝』を調査してクイズ動画を制作したり、学んだことを活かした探究学習『Dゼミ』に取り組んだりしています。また、昨年度から本校には県外や海外の方も多く来校しました。交流を通して様々な文化を学び、理解を深めることもできました。
『大東愛プロジェクト』は、未来まで大切につないでいきます。
竹灯籠づくり(福井市:殿下中学校)

世代を超えて地域を盛り上げようと、公民館が企画した竹灯籠づくりに、
小学生とともに参加しました。
地域の方の手ほどきを受けながら24本の灯籠を完成させました。
11月に地域の方の作品とともに公民館周辺に飾られ、幻想的な光を放っていることでしょう。
文殊山強走大会(福井市:足羽中学校)

地域の象徴である文殊山を眺めながら、学校南側の田園コース3kmを走り抜きます。目的やコースを変化させながら、回を重ねること56回(令和6年度)を数える伝統的行事となっています。生徒一人一人が自分と向き合い、個々の目標達成に向けて力強く走ることから「強走」大会と銘打たれています。沿道では、地域の方々が大きな声援を送ってくださり、生徒たちの大きな力となるとともに、大会を盛り上げてくれています。
北海道上砂川中学校との交流(福井市:川西中学校)

川西地区出身で明治時代に北海道上砂川町を開拓した山内甚之助氏との縁で、上砂川中学校との交流が続いています。毎年修学旅行で川西地区を訪れてくれた際に、互いの地元や学校の様子、それぞれの近況を紹介し合っています。
カットフルーツ地域販売(福井市:棗中学校)

ブロックの棗祭りに自分たちで作ったカットフルーツを
PTAと育成会と連携してブロックの皆さんに販売しました。
好評で100個余りを完売しました。
鷹巣砂浜マラソン(福井市:鷹巣中学校)

学校横の鷹巣海水浴場で、42回目の砂浜マラソンを行いました。今年は福井伝統工芸アイドルグループ「さくらいと」に応援してもらいました。生徒たちは、心地よい浜風と多くの声援を受けながら砂浜を力走しました。
地域貢献 もりたクリーンピック(福井市:森田中学校)

地域のために何かできることはないかと考えて、森田中生徒会が公民館の協力を得ながら、「街をきれいにするために、競い合いながらも楽しんでできるゴミ拾いイベント」の企画・運営しています。
実行委員は6月から公民館で企画会議を行い、よりSDGsにつながるイベントにするにはどのような工夫が必要かを一生懸命考えてきました。会場準備や受付、ゴミ拾い中の見回り、ゴミの計量やポイント集計、表彰式など、多岐にわたる仕事を当日ボランティアの生徒とも協力しながら頑張りました。森田地区の一員としての自覚を高めています。
国体応援プロジェクト(福井市:社中学校)

福井元気国体・元気大会に向けて、本校生徒会は地域と連携して 「国体応援プロジェクト」に取り組み、国体前日に応援メッセージを掲げ、 完結記念に全校生徒で記念撮影を行いました。
第59回母校訪問駅伝競走大会(福井市:足羽第一中学校)

今年で59回目を迎える母校訪問駅伝が10月9日(水)に開催された。
警察、交通指導員、PTAの協力のもと、母校の小学校の児童、こども園の園児、地域の方が、沿道からたくさんの温かい声援をもらい、選手たちは本当に励まされ、生徒たちは全力で走る姿を見せ、たすきをつなぐことができた。この母校訪問駅伝は、1966年に体育の日が制定されたのを記念して開催されて以来、毎年欠かさず実施されてきた歴史ある行事。
生徒達の保護者や祖父母もこの駅伝に関わっており、3世代にわたって「絆」という「たすき」をつないでいる。さらに、今年10月3日(木)に開催された、県中学校駅伝競走大会で、本校男子駅伝部が見事優勝し、「全国大会出場権」を勝ちとり、全国へと「たすき」をつないでいく。
地域の美しい自然を守る活動(福井市:美山中学校)

美山中学校では、美しい里山の風景を守ろうと、校区内の国道158号沿い3カ所にある総延長500mの花壇に地域の方とともに花の苗を植えたり、サクラマスの卵をふ化させて稚魚を放流したりする活動を続けています。また、生徒会が中心となり、ごみを集めながら校区を巡る「美山クリーン大作戦」を企画し、不法投棄が多い現状を広く伝え解決につなげようとしています。これらの活動が評価され、2025年1月に「環境美化教育優良校等表彰事業」で農林水産大臣賞を受賞しました。
地域と連携した越廼PR活動(福井市:越廼中学校)

地域を活性化させ、地域のすばらしさを県内外に発信していきたいという生徒の願いのもと、総合的な学習の時間「越廼PR」に取り組んでいます。
本校が伝統的に取り組んでいる「さかなまつりでの特産品販売」や「県花水仙の栽培・無料配布」などにおいて、より良いものを目指して話し合いや試行錯誤を重ね、実施してきました。また、SDGsの取組を進めながら、地域の海岸清掃を継続的に行っています。さらに、巨大な竹あかり(竹灯籠)を作成し、地域の夏まつりにおけるフォトスポットとするなど、地域と連携した新たな活動を積極的に行っています。
SKP(清水活性化プログラム)活動(福井市:清水中学校)

中学校区内の4つの公民館とタイアップして地域の活動をしています。
部活動のない水曜日と日曜日に生徒が自主的に活動しています。
世界に拓かれた学教教育 (福井市:福井大学教育学部附属義務教育学校)

シンガポールの高校生をはじめ、
アメリカ、アフリカ、エジプト、台湾などから多くの生徒や先生が来校しました。
これらの交流を通して、様々な国の文化について学び、
また改めて日本文化の良さに気くことができました。
オンラインでの全校集会(福井市:福井大学教育学部附属特別支援学校)

月1回の全校集会は、今年度は新型コロナ感染拡大防止対策として、
一斉には集まらずに各学部をオンラインでつないで実施しています。
画面を介しての双方向のコミュニケーションも上手になってきました。
キャリア教育の充実(福井市:杉坂中学校)

小学校を併設した令和3年度開校の中学校です。
総合的な学習の時間には、教育地域の方々の協力を得ながら、1年を通して職場体験や職業訓話等を中心としたキャリア教育に力を注ぎ、教育目標である「他者とともに、たくましく、正しく生きる力の育成」の具現化を目指しています。
職場体験では、消防署や洋菓子店で出向き2日間しっかりと活動しました。働く目的や意義などの話をお聞きした後、様々な仕事の体験をしました。職業訓話では、室内インテリアやクリーニング業の方の話を聞いたり、クロスの貼りなどの体験をしたりました。
実際に話を聞いたり体験することで、自分自身の将来について考えたり、適性を見つけることにつなげられています。
吉田ブロック
地域・卒業生に守られ20年以上続いている行事(永平寺町:松岡中学校)

1.「松岡発見伝ウォークラリー大会」
地域にある「松岡かるた」を元に、松岡中学校校区内の歴史ある場所を探索し、クラス対抗でポイントを競う行事です。PTAの方にも協力いただいています。1年生がふるさと教育でVRにまとめました。
2.「お帰り松中生」
同窓会の協力のもと、卒業してから30年目の卒業生を母校にお招きし講座を開き中学生へのアドバイス(「職業観」「社会での生き方・考え方」)をいただく時間を設けています。「自分の生き方」について考える時間となっています。
地域へ飛び出すふるさと探究学習(永平寺町:永平寺中学校)

永平寺中学校では、ふるさと探究学習を通して地域住民の『幸せ』をテーマに活動しています。町に子育て世代を呼び込むために『アユつかみイベント』を開催したり、地場産の特産品を用いた商品を「大灯籠流し」で販売したりしました。また、老人福祉センターに出向き、永平寺中オリジナル健康体操を披露したり、永平寺町への誘客をねらい福井駅でパンフレットを配ったりしました。
地元の方の協力の下、学校の外にどんどん出て行って、リアルな人との交流や、実物を見る・触る体験を通して、生徒たちは一歩ずつ成長しています。
地域と共に(永平寺町:上志比中学校)

本校では「地域に貢献し応援してもらえる上中生になろう!」をスローガンに、総合でのふるさと探求学習・積極的なボランティア活動・防災教育の充実・地域活動への参画を通して「地域と共にある学校づくり」を推進しています。
大灯籠流しでの地元ハンドボールチーム「ブルーサンダー」ブースのボランティア・上志比地区スポーツ交流会では種目を考案/運営/参加・上志比中学校プール跡地の利活用を町へプレゼン等と自分たち中学生の知恵と力が活かされていることの実感がさらなる意欲へとつながってきています。