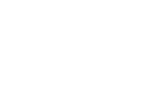特色ある教育活動
南越ブロック
赤米づくり(越前市:万葉中学校)

新元号「令和」の出典でもある万葉集ゆかりの地に、本校は平成8年に開校し、令和7年開校30周年を迎えました。開校2年目より取り組んでいるのが赤米づくり。毎年1年生が田植え、稲刈りを行い、その後生徒ボランティアによって地域の行事で販売しています。
「西っ子合宿通学でのボランティア活動」(越前市:武生第一中学校)

地域と進める体験事業の一環として、
ボランティアで武生西小1~3年の合宿通学のお手伝いをしました。
夕食の準備やお風呂上がりの世話など、
子どもたちはもちろんお母さん方にも大変喜んでもらいました。
武生一中生は、校下4ブロックのそれぞれで、
体育祭や文化祭、老人会などのイベントに参加して地域に貢献しています。
伝統の黒米づくり(越前市:武生第二中学校)

平成11年から始まった黒米づくりは、保護者や地域の方の力もお借りし、本校の伝統的行事となっています。 収穫した黒米を使って、おにぎり、せんべい、地元のケーキ屋さんとコラボしたクッキーをつくっています。
三世代交流村国山清掃ボランティア(越前市:武生第三中学校)

「三世代交流村国山清掃ボランティア」を行いました。
環境美化に取り組む地域自治振興会「クリーンクラブ」の方々の協力を得て、
夫婦池のビオトープの修繕や、スコップで泥のくみ上げなどをしました。
大菊栽培(越前市:武生第六中学校)

本校の大菊栽培は、1979年から続く伝統ある活動です。
地元王子保地区の菊づくり名人指導のもと、一つの鉢から三つの花を咲かせる「大菊三本立て」を栽培しています。2016年からは「たけふ菊人形」への出展も行っています。
春の苗の植え付けに始まり、PTAとも協力しての休日の水やり、秋の輪台取り付けなど、定期的な菊の世話とその成長を見守る活動を通して、苦労が報われる喜びや命を育てる責任を感じるとともに、生徒の心の成長を図る体験活動となっています。
毎年10月頃には大輪の花を咲かせ、公民館、小学校、こども園に展示するなどして、地域の方々にも鑑賞していただいています。
地域と協働した探究学習(越前市:武生第五中学校)

本校は、地域の活性化につながる活動を生徒が主体的に企画・実践し、活動の成果を文化祭など学校行事や地域の行事の中で発表している。
地域の特産物であるすいか栽培や希少植物であるさぎ草栽培などを教育活動に取り入れながら、生徒主体の探究的な学びの推進に取り組んでいる。
越前和紙でのコサージュづくり(越前市:南越中学校)

ふるさとを愛し、誇りに思う生徒の育成を目指して、PTAの3学年委員の方々に協力をいただきながら、3年生が卒業式の時に胸に飾るコサージュづくりに取り組んでいます。
コサージュは、校区内の岡本地区で1500年の伝統のある越前和紙を使用しています。卒業式への思いを高めるとともに、地域の伝統産業への理解と愛着を深めるよい機会となっています。
東京都立芝商業高等学校との交流(池田町:池田中学校)

池田町は東京都立芝商業高等学校とまちおこしの提携を結んでおり、高校生が農産物や特産品を文化祭等で販売するなど、商品流通の学習を行っています。池田中学校の生徒も高校生と直接交流したり、修学旅行での特産品版売についてアドバイスをもらったりしています。
ふるさとの未来を考える「子ども議会」(南越前町:南越前中学校)

今年度から実施の「子ども議会」は、「南越前町のよさや課題を探り、その解決のための方策を考え出すことにより、町の未来創造の当事者として、町及び自身の未来に向けて夢と希望をふくらませる契機とする」ことを目的に、ふるさと学習の一環として実施されました。
今回は3年生全員が参加し、総合的な学習の時間を使って町の課題を検討し、質問書を作成しました。議会当日には、議長役と議員役の計12人の生徒が実際の議場に立ち、役場の各課担当者や町長から丁寧に答弁を受け、生徒たちは自分たちの意見が真剣に受け止められていると実感しました。その誠実な対応により、「頑張って良かった」という思いも一層強まったようです。
その他
「花はす早朝マラソン大会」ボランティア活動(南越前町:南条中学校)(2022年3月 南越前中学校に統合)

南越前町主催の「花はす早朝マラソン大会」には、全校生徒の半数以上、
教職員の8名がボランティアとして自主的に参加しました。
生徒は、午前4時30分に、教職員は午前4時に集合し、大会運営に関わる様々な業務の手伝いをしています。
中学生ボランティアの参加がなくては大会運営に支障をきたすほど、絶大な貢献をしています。
ふるさと再発見学習(南越前町:今庄中学校)(2022年3月 南越前中学校に統合)

地域の姿を多面的に捉え、地域の未来を考える活動を毎年1年生で行っています。
たくさんの地域の方々にご協力頂き、古里今庄を知るいい機会となっています。
ふるさとを愛する心を育む(南越前町:河野中学校)(2022年3月 南越前中学校に統合)

河野中学校では毎年、町のご協力によりふるさと学習の一環として梅の収穫と加工を行っています。
梅干しができあがるまでの作業体験を通して、
ふるさとへの愛着を持てるように指導していきたいと考えています。